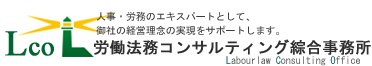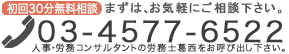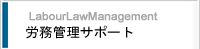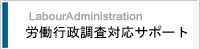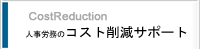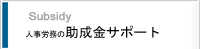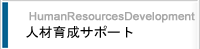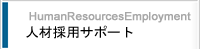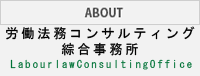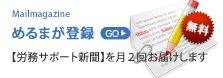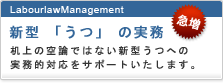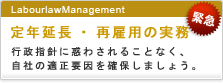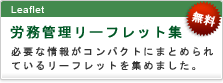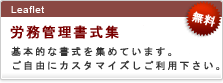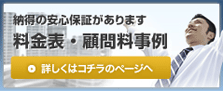���ʎ�`�A���X�g���ȂNj}���Ȑl�����x�̕ω��A����ɘJ�����Ԃ̑���ɔ����A�r�W�l�X�}���̃X�g���X�͓������ɋ����Ȃ��Ă���܂��B���������g�̓I�E���_�I���N������u���Ă����Γ��R�A�Ɩ��Ɏx��𗈂��܂��̂ŁA�{�l�����łȂ��o�c�҂ɂƂ��Ă��d�v�ȉۑ�ł��B
�J���s���ɂ����Ă��A�u�J���҂̌��N�����v���_����A�����ԘJ���ɑ���K���A���N�Ǘ��ׂ̈̎w�j�A�X�ɂ͉ߘJ���E�ߘJ���E�̋Ɩ��ЊQ�̔F�����A�����Ď��ԊO�J���ɑ��銄�������̎x�����̓O�ꓙ��ϋɓI�ɍs���Ă��܂��B����5�N�ԂŘJ����@��37���ᔽ�Ƃ��ēE�����ꂽ���Ə�́A��3�{�ɂ̂ڂ��Ă���ƌ����Ă��܂��B
���̂悤�Ȏ���I�w�i�܂��A��Ƃ́A�J���s���̎d�g�݂����Ď��ԊO�J���y�ь��N�Ǘ��ɑ���w�������ւ̑Ή����@��m���Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B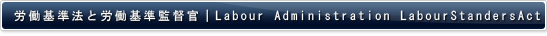
| �J����@�̖@�I���i�ƘJ����@��������J����ē��̌����Ƃ��̌��E�ɂ��Ēm���Ă������Ƃ���Ƃ̃��X�N�}�l�W�����g�Ɍ������܂���B |
 |
�J����@�̏����Ώێ� |
| �J����@���ᔽ�����ꍇ�̏����̑Ώێ҂́A�u�J���҂Ɋւ��鎖���ɂ��āA���Ǝ�̂��߂ɍs�ׂ����邷�ׂĂ̎ҁv[1]�ƂȂ��Ă��܂��B�u�J���҂Ɋւ��鎖���ɂ��āA���Ǝ�̂��߂ɍs�ׂ����邷�ׂĂ̎ҁv�Ƃ́A�����̎x����J�����Ԃ̊Ǘ��Ȃǂɂ��Ă̌����̐ӔC�҂̂��Ƃ��w���܂��B�Ⴆ�A��@�Ɏ��ԊO�J���������Ă����ꍇ�A������A���Y���ԊO�J���̋Ɩ����߂��Ă���������ے����������̑Ώێ҂ƂȂ�܂��B�������A�u�J���҂Ɋւ��鎖���ɂ��āA���Ǝ�̂��߂ɍs�ׂ����邷�ׂĂ̎ҁv�����������̑ΏۂƂ���ƁA�ᔽ��Ƃ������̐ӔC�҂ɐӔC��]�ł���\��������̂ŁA�����K��[2]��݂��A������ے�������������̂ł���A���̗��v�A���҂ł���@�l���̂��̂������̑ΏۂƂ��Ă��܂��B �����K��́A���Ǝ�̉ߎ��𐄒肷��@�\��L���܂��B [1] �J����@10�� [2] �J����@121�� |
|
 |
 |
�J����ē��Ƃ� | ||||
|
�J����ē��́A�@�ᔽ�����A���������邽�߂ɁA��Ɏ��̌�����L���Ă���B�J����ē��́A���ʎi�@�x�@�E���Ƃ��āA�B�̌������L���Ă��܂��B
[1] �J����@102�� |
|||||
 |
 |
�J����ē��̌����̌��E |
| �O�q�̂Ƃ���A�J����@�ł́A�Ռ��A���ޒ�o�̗v���A�q��A�𖽂��錠���A����ɂ͎i�@�x�@���̌����Ƃ������l�X�Ȍ�����J����ē��ɗ^���Ă��܂��B�����āA���̌����̍s�g�̕��@�E���x�͘J����ē��̍ٗʂɈς˂��Ă����܂��B�������A�ē��̍ٗʌ��͖������ɋ������킯�ł͂���܂���B�ٗʌ��̈�E�E���p������A��@�ȍs���w���ƂȂ�A�s�������i�ז@��̍R���i�ׂ̑ΏۂƂȂ� ���܂��B |
|
|
��O�\��� �s���w���ɂ����ẮA�s���w���Ɍg���҂́A���₵�������Y�s���@�ւ̔C�����͏��������͈̔͂���E���Ă͂Ȃ�Ȃ����Ƌy�эs���w���̓��e�������܂ł�������̔C�ӂ̋��͂ɂ���Ă̂ݎ����������̂ł��邱�Ƃɗ��ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�Q�@�s���w���Ɍg���҂́A���̑�������s���w���ɏ]��Ȃ��������Ƃ𗝗R�Ƃ��āA�s���v�Ȏ戵�������Ă͂Ȃ�Ȃ��B
|
|
|
�܂��A����ł��A�J����ē����s���s���w���ɂ��A�ē��̍s�g�́A�����܂Ől�Ԃ̐����E�g�̂ɑ���댯���ؔ����Ă���Ƃ��Ȃǂ��������R�ٗʂł���A�Ƃ���Ă��܂��i�哌�}���K���������Ŕ� �g1.10.19�j�B����ɁA�J����ē��̎g���́A�J���҂̌ʓI�ȕی�ł͂Ȃ��A�g�p�҂̒E�@�s�ׂ������܂�A�����ɂ��������Ə�̈�@�s�ׂ����邱�ƂɂȂ�A�Ƃ�����Ă��܂��i�����������n���r53.9.30�j�B�����āA���̍s���葱���Ɋւ��āA�s���葱�@��R�Q�����A������̔C�ӂd���A���}�I�ŁA���������x�ɂ�����K���葱���̕ۏႪ�Ȃ���Ȃ���Ȃ�Ȃ����̂Ɖ�����܂��B ���̓_�A����قɂ����Ă��A���t������b�i�ǒ��l�j�����l�Ȏ�|�ŘJ����ē��̌����ɂ��Ĕ������Ă���悤�ł� [1] �J����ē@�ւ̖����̎�ӏ��i����22�N10��29����o�@�����103���j http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/a176103.htm �O�c�@�c�����c�g���N��o�J����ē@�ւ̖����Ɋւ��鎿��ɑ��铚�ُ� �i���t�O��176��103���@����22�N11��9���j http://www.shugiin.go.jp/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b176103.htm |
|
 |
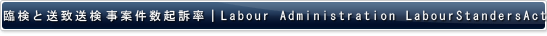
| �J����ē��ɂ��Ռ��̎�ށA����A�Ռ��̎�Ȓ������ځA�Ռ��̌����A���v�����̌����ƋN�i����m���Ă����܂��傤�B |
 |
�Ռ��͂ǂ̂悤�ȗ���Ŏ��{����邩 |
| �Ռ��́A�����ł��ōs�Ȃ���ꍇ������A�\�ߓd�b��e�`�w�ɂėՌ����s���|�̒ʒm�����͂��ꍇ������A����͑�܂��ɐ�������Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B�܂��A�O�q�̂Ƃ���A�s���w���͑�����̔C�ӂ̋��͂̂��Ƃɐ��藧���̂ł��邽�߁A�����̒�����\���o�邱�Ƃ͓��R�\�ł��B |
|
| ���Ƃ̊T���A�J�������E�Ζ��̊m�F�A���S�E�q���Ǘ��̔c���E�m�F | |
 |
|
| �J���@���W���ނ̊m�F | |
 |
|
| �J���ҁA�g�p�ҁi���Ǝ�j����̎��Ԃ̎����A�W���ނƂ̏ƍ� | |
 |
|
| �����������A�w���[�̌�t | |
 |
|
| �������̒�o | |
|
��������@��R����i�J���Җ���A�����䒠�A�o�Ε�j ���g�D�}�i���ȕ\�Ȃǁj ���p�\�R���ғ��L�^�A�^�C���J�[�h ���A�ƋK���A���̑��ЋK�Б��i���^�K�����j ���J�g����i36���蓙�j �����N�f�f�̋L�^�i�ٓ����A����A���ꌒ�N�f�f�j �����S�Ǘ��ҁA�q���Ǘ��ҁA�Y�ƈ㓙�ɌW���o���� �����S�q���ψ���A�q���ψ���̋c���^ |
|
 |
 |
�Ռ��ɂ���Ȏw�����ĂƎw������ |
|
�����J���ǂ̔��\[1]�ɂ��ƁA��Ȏw����������юw�������͎��̂Ƃ���B �i�P�ʁF�����j 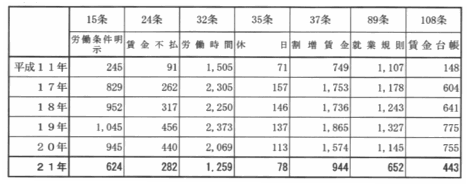 [1] �����J���Ǖ����Q�Q�N�T���Q�P�����\�����@�����Q�P�N�Ɏ��{��������ē��̎��{���� http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2010/20100521-kekka/20100521-kekka.pdf |
|
|
�J����@��R�Q���i�J�����ԁj�ɂ��Ă̈ᔽ���� ���ԊO�J���Ɋւ��鋦��̒����y�ѓ͏o���Ȃ��̂ɁA�J���҂ɖ@��J�����Ԃ��Ď��ԊO�J�����s�킹�Ă�����́B�܂��A����̒����y�ѓ͏o�͂�����̂́A���̋���Œ�߂����ԊO�J���̌��x���Ԃ��Ď��ԊO�J�����s�킹�Ă�����́B |
|
|
�J����@��R�V���i���������j�ɂ��Ă̈ᔽ���� ���ԊO�J���A�[��J�����s�킹�Ă���̂ɁA�@�芄�������i�ʏ�̒����̂Q���T���ȏ�j���x�����Ă��Ȃ����́B |
|
 |
 |
���v�E�������ĂƋN�i�� | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
�J����@�ᔽ�ɂ��A���@���֑��v�E�������ꂽ���Ă���ь����͎��̂Ƃ���ł�[1]�B �i�P�ʁF�����j
�����s���ᔽ�ɂ��Ă͂S�O�O�����A�T�O�O�����ƂȂ��Ă��著�v�E���������������̂�������܂����A���������ɂ��Ă͂S�O����Ƃ����킸���Ƃ����܂��B����́A�O�q�̂Ƃ���A�J����@�́A�J���҂̐������m�ۂ̂��߂ɁA�J�������̍Œ���ݒ肵�Ă���@���ł���A�J���҂̂��L���Ȑ����̎�����}���Ă���@���ł͂Ȃ�����ł��B�܂�A�����̑S�z�s�����͐����������������A���������̕s�����ɂ��ẮA��b�������Œ�����Ɠ����x�łȂ�����A���������������������x�̈ᔽ�łȂ��ƍl�����邩��ł��B [1] �o�T�@�����J���ȁu�J����@�Ɋ�Â��ēƖ����{�v �i�P�ʁF�����j
�J����@�ᔽ�̋N�i���͕��ςQ�O���ƒႢ�̂ɑ��āA�J�����S�q���@�̋N�i���͕��ςU�O���ƍ����Ȃ��Ă��܂��B�������̊m�ۂƂ������_����l����ƁA�J�������Ɋւ���ᔽ��萶���̈��S�Ɋւ���ᔽ�ɂ��ďd����u����Ă��邩�炾�Ƃ����܂��B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
�J����ē��ɂ��Ռ��̐����������� |
| �s�̂���Ă��鏑�Ђ�Љ�ی��J���m�̃T�C�g���ŘJ����ē��̎w���͋����͂̂�����̂��ƕ\�����Ă�����}�̂������܂����A����͌��ł��B �m���ɘJ����ē��ɂ͗Ռ����̌���������A�i�@�x�@�E���Ƃ��Ă̌���������B�������A�Ռ��͍s�������ł͂Ȃ��s���w���ł���A���̌����̍s�g�͗}���I�łȂ���Ȃ�܂���B�܂��A���������������ᔽ�łȂ���Α��v�E�������s���錏���͏��Ȃ��A���������̖������̂悤�ɐ��������������̂łȂ���A�N�i���͌����č�������܂���B�ȏ�܂��A��Ƃ͘J����ē��̗Ռ��ɑΉ����ׂ��ł��B |
|
 |
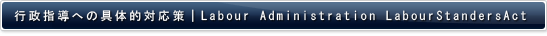
 �����q�w�����̐��������x�ɂċߓ����Ɍ��J�\�� �����q�w�����̐��������x�ɂċߓ����Ɍ��J�\�� |
|
 |