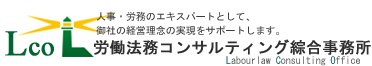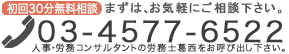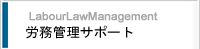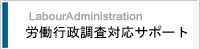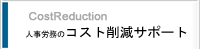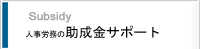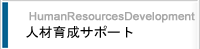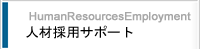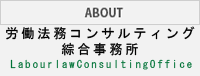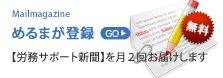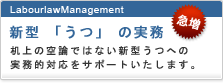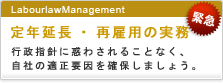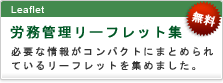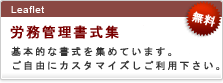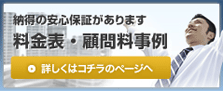数年前と比較すると、企業内の精神疾患事案は複雑化しています。当初は「うつ病」や「抑うつ状態」という診断書が多く、その後、「パニック障害」「適応障害」などの診断書が見られるようになりました。近年は、「パーソナリティー障害」や「新型うつ(病)」と呼ばれる事案も増えてきています。また、再発症して再休職する事案も増えてきています。再発症では初回よりも症状が重くあることが多く、再休職の期間も長くなる傾向が見受けられます。
一方で、企業が置かれた状況も厳しくなってきています。「よく分からないままの安全策」から「一応理解した上で当該事案に適当な策」へと変わりつつあります。
ここでは、特に昨今の人事労務部門を悩ます「新型うつ」および「他責攻撃型」への対して、企業が毅然としてどのおうな対応を取るべきかを書いていきます。