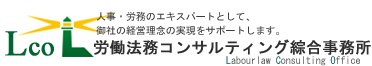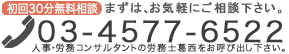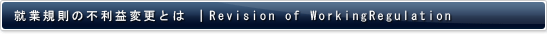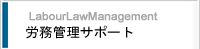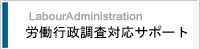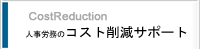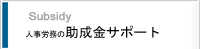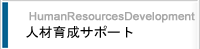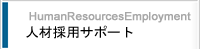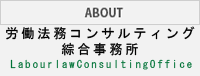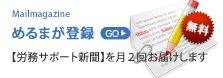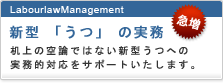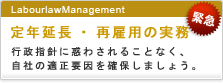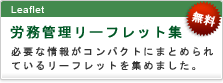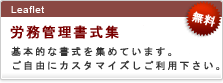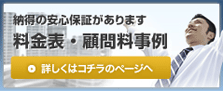�A�ƋK�����Г����[����Ј��̃��`�x�[�V�����A�b�v�̂��߂ɍ쐬���ׂ��ł͂���܂����i���j�B�����āA�J���@���Ȃ���@�����ێʂ������č쐬���ׂ��ł�����܂���B�s�̂̏��Ђ�J���ǂ����Ă��鐗�^�A�ƋK���ɂ�炸�A�܂��A����̎Г����[�����K�肷��̂ł��Ȃ��A�J�g�̗��v�Η��̏�ʂ�z�肵�A��Ƃ́u����v�ƂȂ�悤�ȏA�ƋK�����쐬�E�^�p���邱�Ƃ��A�^�ʖڂōv���I�ȎЈ��ɂƂ��ėǍD�ȐE����̎����ɂȂ���A��Ƃ̌o�c���O�̎����ɂȂ���܂��B
�i���j�Ј��̃��`�x�[�V�����A�b�v�͊�ƂɂƂ��Č������܂��A�命���̐^�ʖڂōv���I�ȎЈ��̃��`�x�[�V�����A�b�v�̎d�g�݂͐l�����x�Ŏ������܂��B���Ј��ƑΛ�����Ƃ��ɕ���ƂȂ�A�ƋK���ƎЈ����琬����l�����x�̖������S���ӎ����邱�Ƃ���ł��B
 |
�_��Ƃ��Ă̏A�ƋK�� |
|
����̕ω���ٗp�`�Ԃ̑��l���A�J���҂̈ӎ��ω���w�i�ɁA�g�p�҂ƘJ���҂̊W�́A�u���s����_��ցv�ƈڍs���Ă��܂��B����ɂƂ��Ȃ��A�A�ƋK�����S���u�_��v�Ƃ��Ă̖����́A���ĂȂ��قǏd�v�ɂȂ��Ă��܂����B�_��ł���ȏ�A�A�ƋK���́A�@������o�c���ɂ���āA����I�Ɍ��������s����ׂ��ł��B |
|
 |
���v�Η��̏�ʂŁu����v�ƂȂ蓾�邩�H |
| �Г��K���̒��ŁA�A�ƋK���قNj��ԈˑR�̂��̂͂Ȃ��ł��傤�B�قƂ�ǂ̊�Ƃ̏A�ƋK���́A�J�g�W�̒������j�́u�╨�v�ł���A�J���֘A�@�K�����̂��тɌp�������ꂽ�u�ٌ`�v�Ƃ����Ă��ߌ��łȂ��Ƃ�����ł��傤�B����ł���Ƒg�D�������̂́A�A�ƋK�����g���Ă��Ȃ����炾�Ɛ��@�ł��܂��B�Ɩ����߂��]�Ζ��߂����߂���邱�Ƃ͂Ȃ��A�قƂ�ǂ��ׂĂ��J�g�̍��ӂłȂ���Ă���̂����{��Ƃ̘J���Ǘ����Ƃ����܂��B���ق⒦�����ł��鎖�Ăł����Ă��A�����̏ꍇ�͑ސE��w���Ƃ����`���Ƃ��Ă��܂��B �������A���ꂩ��͏A�ƋK�����@�\���Ȃ���Ȃ�Ȃ�����ɂȂ�ł��傤�B�����ٗp�V�X�e���̕ϗe��w�i�Ƃ��āA�ʘJ�g�W�ł̕������������邱�Ƃ́A�o�傹����Ȃ����ゾ����ł��B�����ł́A�A�ƋK���́A��Ƃ̗B��́u����v�ƂȂ�܂��B�J�g�W������c�[���ł͂Ȃ��A�܂��ɑΗ������ʂŊ�Ƃ�D�ʂɗ�������u����v�Ƃ��Ă̏A�ƋK������ƂɕK�v�Ȏ���ɂȂ����Ƃ����܂��B �����Ƃ��A���̋K���ނ�_�ƈقȂ�A�A�ƋK���́u�q�g�v�ڂ̑ΏۂƂ��܂��̂ŁA�A�ƋK���͌��ʂƂ��Ă̌����`�������u���������v�Ƃ��Ă̌����`���ł��邱�Ƃ�F�����邱�Ƃ��K�v�ł��B�����āA��Ƃ̌����͍s�g���ꂸ�A��Ƃ̋`���͒��J�ɗ��s����邱�Ƃ��]�܂����J���Ǘ��ł��B�u����v�͋����ɂ��������Ƃ͂Ȃ����A���́u����v���g��Ȃ��悤�ȘJ���Ǘ���S�����邱�Ƃ��]�܂������Ƃ͌����܂ł�����܂���B |
|
 |
�A�ƋK�����g����ʂ�z�肵�č쐬���Ă��邩�H |
| �w�A�ƋK�����Г��̃��[���u�b�N�x�Ƃ����Ă����ƂقǁA���v�Η��̏�ʂŘJ���ґ��̎咣�ɋ����Ă��܂����Ƃ������̂����ۂ̂Ƃ���ł��B�ʏ�̘J���Ǘ��ł́A�A�ƋK���͎g���Ă��܂���B�����炭�A�����̊�Ƃ�����ɂ����ďA�ƋK����ڂɂ��邱�Ƃ͂Ȃ��ł��傤�B���������Ɍ����ƁA����̘J���Ǘ��ɂ����ẮA�A�ƋK���Ȃg�킸�ɁA�m�炸�m�炸�̂����Ɍʓ��ӂ�X�^���X�ŘJ���Ǘ����s���Ă���Ƃ������Ƃł��B�������A�����́A�A�ƋK���ŋK�肳��Ă���ȏ�ɘJ���҂ɂƂ��ĉ��b�I�Ή������Ă��邱�Ƃ������Ƃ��܂��B �ł́A�A�ƋK������������o���Ă���Ƃ��́A�ǂ�ȏ�ʂł��傤���H����́A�ʓ��ӂ�����ꂸ�A�J�g�����֔��W���Ă��܂����ꍇ�ł��B�A�ƋK���́A�J�g�̗��v�Η��̏�ʂŁA�͂��߂ĔF��������̂ł��B�����炱���A�Г����[���Ƃ������v�����c�[���ł͂Ȃ��A�A�ƋK���͊�Ƃ����u����v�łȂ��Ă͂Ȃ�܂���B |
|
 |
�ǂ������ꍇ�Ɂu�s���v�ύX�v�ƂȂ邩�H |
| �A�ƋK���̉����i�߂�ɂ������āu�ǂ������ꍇ���s���v�ύX�ƂȂ邩�v��m��K�v������܂��B�s���v�ύX�ɍ����������邩�ǂ����͊W����܂���B�s���v�ύX���ǂ����́A�J�������̐�������ł��Ⴍ�Ȃ�A�u�s���v�ύX�v�ƂȂ�܂��B�Ⴆ�A�J�������̐��������シ�鎖�����������Ƃ��Ă��A�J�������̐������ጸ���鎖������ł�����ƁA�u�s���v�ύX�v�ɂ�����ƔF�����Ȃ���Ȃ�܂���B �܂��A�ʓ��ӂ����ꍇ�́A�u�s���v�ύX�v�ƂȂ�Ȃ����Ƃ͓��R�ł��B�ʓ��ӂ����Ȃ����߁A����I�����I�ɘJ���������K�肷��A�ƋK��������I�ɕς��邱�ƂŁA�J��������ύX���邱�Ƃ��u�s���v�ύX�v�ƌĂт܂��B |
|
 |
�s���v�ύX�́u�������v�Ƃ́H |
| �A�ƋK���̕s���v�ύX�ɂ�����ꍇ�ɍl���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�L���E���������߂�“�}�W�b�N���[�h”�ł���s���v�ύX�́u�������v�ɂ��Ăł��B �J���_��@��10�����l��s�����i�Ŕ�H9.2.28�j�ň��p����Ă���u�������v�ł��B�J���_��@��10�������p����A�u�A�ƋK���̕ύX�ɂ����鎖��v�Ƃ��� �@�u�J���҂̎�s���v�̒��x�v �A�u�J�������̕ύX�̕K�v���v �B�u�ύX��̏A�ƋK���̓��e�̑������v �C�u�J���g�����Ƃ̌��̏v�̂S�_�������A�����ɂ��āu�����I�v�Ȃ��̂ł���Ƃ��́A�J���_��̓��e�ł���J�������́A�ύX��̏A�ƋK���ɒ�߂���e�ƂȂ�A�Ƃ���Ă��܂��B |
|
 |
�u�������v�͍��o������ |
| �A�ƋK���̕s���v�ύX�����{����ۂɁA�ύX���e���̂����������ǂ�������������̂͋ɂ߂ăi���Z���X�ł��B�������̗L����ٌ�m��Љ�ی��J���m�ƕG��˂����킹�Ĉ����������Ƃ������Ǝv���܂����A����͕s���v�ύX�ɂ����Ċ�Ƃ��ł��̂��Ă͂����Ȃ����Ԃ̎g�����ł��B �O�q�̂S�_�̂����A�d�v�Ȃ͇̂C�u�J���g�����Ƃ̌��̏v�ł��B�ٔ������ƂȂ����ꍇ�ɏd�������̂́A�u�J���g�����̌��v�Ƃ����v���Z�X�ł��B ����āA�J���҂̈ӌ����A�s���v���ւ���[�u���u���A��ƂƂ��Ă̕K�v�����������ȂǁA�J�g�Ԃ̗��v�����Ƃ����v���Z�X�J�ɍu���邱�Ƃ�������̍ő�̃|�C���g�ł��B |
|
 |
�A�ƋK���s���v�ύX�̌����I�l���� |
| �����I�ɂ́A�u�ٔ������ɂȂ�Ȃ���A�A�ƋK���ύX�̍������͖���Ȃ��v�Ƃ������Ƃ܂��Ă����Ȃ���Ȃ�܂���B�u�ٔ������ɂ��Ȃ��v�Ƃ����_�ƁA���ɍٔ������ƂȂ����Ƃ��Ă��C�u�J���g�����Ƃ̌��̏v�Ƃ����v���Z�X���d�������A�Ƃ����_���l�����킹��ƁA��Ƃ̎����Ƃ��Ƃ�ׂ���i�́A���̃v���Z�X�J�ɍu���邱�Ƃɐs���邱�ƂɂȂ�܂��B��̓I�ɂ́A�J���҂̈ӌ����A�s���v���ɘa����[�u���u���A�g�p�҂Ƃ��Ă̕K�v����������܂��B���̌��ʂƂ��āA����Ӗ��ł́u�K�X�����v���Ȃ���āA�ٔ������ɂ܂Ŏ���Ȃ����Ƃɍςޏꍇ�������Ƃ����܂��B ���̈Ӗ��ŁA�A�ƋK���́u�������v�͏��^�̂��̂ł͂Ȃ��A��Ƃ̓w�͂ɂ��A�쐬�������̂Ȃ̂ł��B |
|
 |
�J���҂̍s�ׂ�v���Ƃ��Ă��Ȃ����H |
| �A�ƋK���͘J�g�Ԃ̖����I�Ȍ����`���W���K�肷����̂ł��B������̍s�ׂ��Ȃ��Ă����͂���������g�p�҂̌`�����Ƃ��ẮA���فE�����E�z�u�]���Ȃǂ̊e���������݂��܂��B �J���_��ł́A���ɉ��ق�]�Ȃǂ̌`�����̍s�g�Ɋւ��A�������p�����ƂȂ�܂����A���̔��f�ɂ����Ă̓v���Z�X���d������A�����ł͘J���҂̂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����������]������Ă��܂��B �������A�A�ƋK�����@�\����̂́A�J���҂��g�p�҂̗v�������ۂ�����ʂł��B���邢�͗��Q���Η������ʂł��B���̂��߁A�{���s�v�ȘJ���҂̍s�ׂ����Ƃ�����͔����́u�v���v�Ƃ�����A�s�ׂ��Ȃ���Ί������Ȃ��A�ƋK���͑S���g�����̂ɂȂ�܂���B�v���Z�X�𗚍s���悤�Ƃ���u�w�́v��u�p���v�́A�R�~���j�P�[�V�����Ƃ��Ă͕K�v�ł����A�v���Z�X�Ɏg�p�҂��S������Ă͈Ӗ�������܂���B �n�������Ƃ��Ă����Ȃ��Ă��Ȃ��Ă͈Ӗ����Ȃ��B�ސE�͂��łȂ��Ƃ��@�|���قŏI��点�������Ă͏��Ȃ�����܂���B�J���_������Ȃǂ̘J���҂̕s���v���傫�������́A�g�p�҂����Ŋ����ł��邱�Ƃ��s���ł��B |
|
 |
�}�j���A�������Đl�����傪����𐧖Ă��Ȃ����H |
| �J����@�́A�������قɂ��āA�J����ē����̏��O�F���K�v�Ƃ��Ă��܂��i��20���3���j�B���̏��O����ɂ͐��T�Ԃ�v����ꍇ�����肠���B�������ٌ�ɏ��O�F���\�����Ă������ᔽ�ł���A�U�����ȉ��̒����܂��͂R�O���~�ȓ��̔����ɏ������Ă��܂��܂��i��119���1���j�B�ᔽ���Ă��������ق͖����I�ɓ��R�ɖ����ƂȂ���̂ł͂Ȃ�܂��A�J����ē�������w�����邱�ƂɂȂ�܂��B ����́A�A�ƋK����l������̃}�j���A���Ƃ��ċK�肵�Ă��邱�Ƃɖ�肪����܂��B�A�ƋK���͘J���҂Ǝg�p�҂Ƃ̊Ԃ̌����`���W���K�肷����̂ł���A�����Ɏg�p�҂̃}�j���A�����L�ڂ���ƁA�J���҂ɑ���g�p�҂̋`���ƂȂ��Ă��܂��܂��B���ɁA�}�j���A���ɔ������ꍇ�A�g�p�҂̌����s�g�������ƂȂ�����ɓ����\�����傫���Ƃ����܂��B �������قŏ��O�F��\�������邱�Ƃ́A�A�ƋK���ɏ����ׂ��ł͂���܂���B�܂��A�����̂����鍐�m�����葱���́A�葱�����u�����Ȃ��ꍇ�܂Ŕ����ċK�肷�邱�Ƃ����߂��܂��B���������A�������ق����قɌ��邱�Ƃ������ł͂���܂���B �A�ƋK���͖��R�ƎГ��葱���[�����L�ڂ��ׂ��ł͂Ȃ�܂���B�����s�g�̎菇�͎Г��ב��ȂǑ����ɋL�ڂ��ׂ��ł��B�A�ƋK�����@�\���ׂ����Ăł́A�}�j���A���������A�ƋK���́A�������ĘJ���҂𗘂��邱�ƂɂȂ肩�˂܂���B |
|
 |
���������ĉߓx�Ɋm��I�ɂȂ��Ă��Ȃ����H |
| �x�E�ɂ��ẮA���_�������Ă̋}���ɂ��A�A�ƋK������������i�߂Ă����Ƃ��������Ǝv���܂��B�ʎZ�K���݂���ꍇ�A���̊��Ԃ��o�߂���ΒʎZ���Ȃ��|�m�ɋK�肷�������������܂��B ����́A�P�O�N���Ԃ������Ă��ʎZ��F�߂�̂��Ƃ����^�₩�炾�Ɛ��@���܂����A���m�ɏ������ƂŁA���̊��Ԃ��o�߂�����Z�b�g���邱�Ƃ�J���҂ɖ��Ă��܂��A�J���҂����Z�b�g���錠����L���邱�ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B�g�p�҂ɂƂ��ẮA�ʎZ�K�肪�Ȃ������܂����߂ő�����]�n������Ƃ����܂��B �܂��A�J���҂́A���E���烊�Z�b�g���Ԃ��邱�ƂŁA�x�E���Ԃ̒ʎZ�Ɏ���ɂ悤�Ɋ撣�葱���Ă��܂��B�Ĕ����Ă��A�Ȃ��Ȃ��x�E���Ȃ��B����ɁA�x�E�̑O�ɒ����A�������K�肷��A�ƋK���ł́A�o�ƌ����f������ł͋x�E�v���������Ƃ��ł��܂���B ���ɂ́A�������قőސE����s�x���Ƃ��������������܂��B�������A�A�����I�ɂ́A�������ق��ނȂ��Ƃ��Ă��A�ސE�����S�z�s�x���ƂȂ邱�Ƃɂ͕s����L����J���҂����Ȃ�����܂���B��������̐�����Z��[���̕ԍςɍ��邱�Ƃ�����ł��傤�B���̂��߁A�ސE���𐿋�����J���R����i�ׂ���N����鋰�ꂪ�傫���ƍl�����܂��B�ߔN�̍ٔ���ɂ́A�������ق�L���Ƃ��Ă��A����z�̖�R���̑ސE��������F�߂����̂�����܂��B �u�A�ƋK���ɏ����Ă��邩��v���邢�́u�A�ƋK���ɂ͏����ĂȂ�����v�Ƃ����āA�A�ƋK���̋K��ǂ���ɉ^�p���A���p�ȕ����������N�����͓̂���Ƃ͂����܂���B�{���͌����ɂ����Ȃ�����A�����ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA�g�p�҂����}�I�ɍs�g����Α����͂��ł��B ��������\���\���Ƃ��������̂��ƂɁu�����������v�ߓx�Ɋm��I�ȏA�ƋK���́A�l�X�ȃP�[�X���z�肳�������̐��E�ł́A�������Ė��ɗ����Ȃ��Ƃ����܂��B |
|